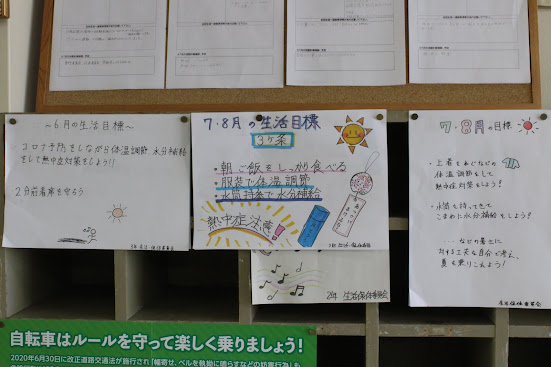猛暑が続いていますが、バドミントン部は元気に練習のため登校してきています。
2021-08-04
バド部の練習 そして 夏休みの宿題?の落とし物
2021-08-03
クロームブックの活用
道外のある小学校での取組状況です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学校生活のさまざまな場面で、児童・教師がICTを積極的に使っています。例えば以下のような使い方です。
・始業式や終業式を教室でオンライン参加する。【行事】
・Googleスライドというプレゼンテーションソフトを使って、自己紹介をする。【特別活動】
・休み時間にタイピングの練習を行う。【休み時間】
・休み時間にプログラミングソフトで遊ぶ。【休み時間】
・Googleスライドというプレゼンテーションソフトを使って、クイズ係がクイズを出題する。【特別活動】
・Google Jamboardというデジタルホワイトボードを使って、意見交換をする。【理科】
・YouTubeを視聴して、地域の様子を理解する。【社会科】
これまでの教師が主に使うICTから、児童自身が文房具として日常的に使いこなすICTへ。みんなで進化していきたいと思います!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
どこの学校も1人1台のタブレット端末の活用について、試行錯誤しながら取り組んでいるようです。
始業式や終業式などの儀式的行事で、タブレットを使うメリットは何でしょうか。児童生徒全員が目の前のタブレットの小さい画面で式を見るよりも、教師が大画面のモニターにその様子を投影したほうがわかりやすいはずです。
1人1台のメリットを生かすのであれば、儀式的行事の在り方について一から検討する必要があります。リモートによる全員参加(児童生徒全員が発言等のアクションをする)の始業式・終業式はありかもしれません。ただ、これには教師の発想の転換(コペルニクス的転換まで求められます)が必要です。
「ただ使えばいい」1人1台タブレットよりも、「児童生徒が確実に情報活用能力を高めることができる」1人1台タブレットのほうがいいに決まっていますよね。
そこに至るためには、やはり授業での活用あるのみです。TRY and ERROR で効果的な活用を探るしかありません。そしてそこで得た成果を共有していくことです。
上記の道外の小学校はとにかく使ってみようという考えで、取り組んでいるようです。使う選択はありです。使ってみて初めて、活用に向かう取捨選択が行われるからです。こんな学校が増えてほしいと思いますし、本校もそうでありたいと思っています。
道内のある小学校の「文房具だから、授業に持って行って使わなければしまえばいい」という取組、これは、そこに費やす時間がかなりの無駄です。これはわかりきっています。なぜなら「使わなければ、活用とは言えない」からです。
とにかく授業で使うこと、これを推し進めていきたいと考えています。
2021-07-28
大船遺跡・垣ノ島遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産に正式登録!
昨日付けで「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されました。臼尻中学校区内の「大船遺跡」と「垣ノ島遺跡」が世界遺産になりました。
本校にとっても喜ばしいことです。
渡島管内では「大船遺跡」と「垣ノ島遺跡」の二つだけが構成資産としてその価値が世界に認められたこと、そして、どちらも旧南茅部町教育委員会を中心に旧南茅部町の人々が大切に守ってきたものであること、まさに南茅部地域の「宝」であることは間違いありません。
さらにはその二つを校区内に含む学校は本校だけです。(尾札部中・磨光小は校区外、大船小は「大船遺跡」のみ、臼尻小は「垣ノ島遺跡」のみ)
統合によって変化はしますが、世界遺産登録時にどちらも校区に含む学校は本校だけです。本校の卒業生は大いに自慢してほしいと思います。
世界遺産登録を祝う本校生徒の集合写真を撮りました。縄文文化交流センターに掲示されています。
ブログなので写真に圧縮をかけています。拡大しても顔がわからないようにしてあります。雰囲気だけを見ていただけたらと思います。
2021-07-27
2021-07-26
GIGAスクール構想 1人1台タブレット端末の夏季休業期間における取組について
文部科学省から7月13日付で発出された文書「GIGA スクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等に向けた夏季休業期間中における取組について」が本日付で函館市教育委員会から参考送付として届きました。
もともとGIGAスクール構想における1人1台タブレット端末(函館市ではクロームブック)は、家庭学習やオンライン学習での活用も想定しています。夏季休業期間中の端末の持ち帰りについても、その取組を積極的に行うことが求められています。
本校では夏休み中の課題について、提出用のGoogleClassroomが設置されており、家庭にあるタブレットやスマホ、パソコン等でレポートを作成し提出できるようにしています。
ただ、生徒に貸与されたクロームブックについては、学校外への持ち出しが禁止されており、文部科学省が求める学習活動ができないでいます。
本校では、タブレット活用のルールが定められており、現在禁止されている家庭への持ち帰りについても、それが可能になった時点で活用等のルールを提示することにしています。
「日常的に使う」ことが求められている1人1台タブレット端末は、家庭学習でも活用して初めて「日常的に使う」端末になっていきます。
早い段階で家庭への持ち帰りや校外での活用を可能にしていくことが、いま求められている児童生徒の「情報活用能力」育成につながるはずです。
「英語の日記」夏休みの課題として設定し、毎日クロームブック等で作成している生徒教科はもちろん道徳科の授業でもクロームブックを使っています。
ヒグマ人身被害多発に係る注意喚起について
北海道環境生活部環境局自然環境課動物管理担当課長より「ヒグマ人身被害多発に係る周知及び注意喚起のお願いについて」文書が届きました。